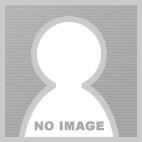本日のレグザ君
ネットで検索するとどうもZX9000の話が出てこないのでもう少し書きたいです。
自分がテレビを選ぶに当たってこだわった点は以下の通り
1.液晶でも高コントラストを実現できるもの
なぜ::前もっていたのは5年前のアクオス
(LC-22AD2
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20031002/sharp.htm)
これでもこの当時はまあまあのスペック・・・でもないや。とにかく液晶を買って後悔したのは寝ながら見る映画の品質がとても悪いこと。
2.自由度が高いこと
なぜ::アクオスでもだいぶいろいろなシステムを載っけてきましたけど、それでもSONYや東芝に比べるとまだまだという感じ。実際には必要充分なんですけど、それを必要と思わせるうまさがない。スーパーのコージーコーナーか、銀座高野のショーケーキ。どちらもうまいけど値段が違うのはそれを容認できるだけの演出がケーキに存在しているから、という風に同じ画質改善機能でも東芝はレゾリューションなんとか、ソニーはDRC-MF V3なんていうかっこいい名前が付いています。
悩んだこと。
まず店頭での画質比較っていうのは悲しいほど役に立ちません。正確に言うとその店舗がどの程度の照明を使っているかによります。秋葉原ヨドバシでやっと薄暗いところでのZXシリーズの展示があって、それでやっとLEDエリア制御の有用性を見いだせたくらいですから、もし実際に近い環境でみたいと望むなら、それなりに店舗をはしごするしかないでしょうね。
ZX9000と比較した機種:SONY XR1 ZX8000 Z8000
XR1の46Vはもう製造中止になったようですが、もしZX9000の発売がなければおそらくこれにしていたと思います。ただ前のアクオスを買ったときに2003年発売のものを買っていたので2008年発表のXR1はやや買うにしては古すぎるというところが引っかかりました。何度も見て、かなり良かったと思いますXR1
継続機が出たらZX9000を売っぱらおうかなとさえ思わせるほどです。逆にZX8000は画質はまあまあにしてもXR1のライバルには全くふさわしくない。ディープラグーンが好きになれませんでした。他にもZX9000にもいえるんですが、電源コードが直付けであったりZシリーズとスタンドの違いくらいしかデザインに差異がなかったり(CELL REGZAが最高峰として存在するからなのかもしれませんけど)XR1のような明確なフラグシップらしさというものを感じないんですよね。ZX9000(Z9000)から、ディープラグーンの部分が落ち着いた感じに(ほとんどフレームは真っ黒に近い)なったのでまあまあ良くなったとは思いますけど。ディープラグーンはZX9000(Z9000)では有って無いような存在感にまでさせられちゃってます。むしろ真っ黒にしてもいいんじゃないのかと思うほど。
あと細川さんだったか、誰かもおっしゃってましたけど、スタンドの葉っぱみたいなデザインはちょっと・・・47Z9000のほうがかっこいいね。
デザインデザイン。ここまでそんな事ばかりですけども、正直昨今の液晶はどれを買ってもほどよく高画質です。少なくとも私の目には。
だからもうデザインとか操作性とか、そういうところで差をつけてくるフェーズに入っていると個人的には思うんですよね。数年前からの液晶からの買い換えでも幸せになれると無責任ながら保証できます。それくらい今のテレビはどれを買ってもだいたい同じ(笑
もちろんこだわったなりに差異はあるんですけどもね。
46ZX9000の詳細レビュー
画質についてはファーストインプレッション通りですが、ZX8000のレビューでLEDエリア制御が保守的な動作にとどまっていると指摘されていましたが、それはそうだと思います。具体的に言うと、たとえばライブ映像があって、真ん中に中島美嘉がいてスポットライトで照らされているような映像で、左半分と右半分のバックライトは消灯しても良さそうなものですが、実際には照度が極限まで絞られる程度です(CCFL機種あるいはエリア制御無しと比較すればやはり黒さは違うけど)なので暗室ではわずかな液晶からの光の漏れが見えます。もっともこれでもかなり高コントラストだと実感は出来ますが。
真っ暗になるときは入力切り替えをしたとき(笑
あるいは画面が暗くフェードアウトしたときですね。ある程度の黒が描写される場面でないとバックライトは消灯しないようです。古畑任三郎のOPではLEDがどんな制御をしているかをよく感じることが出来ます。買った人は見てみてね。
たとえば全体的に曇りのシーンでは意外とLEDが働きません。もちろん全く働かないわけではないんですが、感じにくいのです。明暗が離れていて、それぞれ(暗いところと明るいところ)が固まっている方が得意みたいです。
これ以降はZ,ZX共通ですが、レグザリモコン2は微妙!Z8000の時からもこの操作性に不満でしたが改善されてません!
具体的に言うと「録画リスト」とかいう聞き慣れないボタンを押したとき、内蔵HDD(ZシリーズはLANハードディスクやUSBハードディスク)に録画してあるものが出てくるのですが、レグザリンクで機材を選択しDLNAでX90の映像を再生しているときに押すと、X90の中身がリストされる。一見親切そうですが、再生を停止してから「録画リスト」を押すと内蔵HDDの方が出てくる。要するに再生を停止したらいちいちレグザリンクからDLNA機材を選択しないといけないというわけです。もっとスマートなやり方があるはず。
それとたとえば録画リストを眺めていて閉じたくなったとき、いちいち終了を押す。SONYではホーム内での操作はホームのボタンで抜けられるので操作が自然なんですね。さっとXMBに表示される録画してあるものを確認して抜けたいとき、ホームから指を動かす必要がないSONYに対してレグザは律儀に終了を押させる。とても面倒です。録画リストを再び押したら画面が閉じてほしい。
(ちなみに設定メニューは設定メニューボタンで閉じることが出来る。とても謎だ)
とにかく操作性は悪いですね。でも逆にそれが楽しいのも事実ですけど。細かいのが嫌いな人には、あるいは直感的に操作性を求める人にはレグザは向かないですね。
画質設定にしても幅が広すぎて、とにかく買ってから数時間はこの画質設定と戦うことになると思います。おまかせ設定でもまあまあいいんですけど、9000からその機能のボタンをリモコンから削除したとおり、やはり自分で調節してナンボのREGZAだと思うので是非いじってください。
ネットで検索するとどうもZX9000の話が出てこないのでもう少し書きたいです。
自分がテレビを選ぶに当たってこだわった点は以下の通り
1.液晶でも高コントラストを実現できるもの
なぜ::前もっていたのは5年前のアクオス
(LC-22AD2
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20031002/sharp.htm)
これでもこの当時はまあまあのスペック・・・でもないや。とにかく液晶を買って後悔したのは寝ながら見る映画の品質がとても悪いこと。
2.自由度が高いこと
なぜ::アクオスでもだいぶいろいろなシステムを載っけてきましたけど、それでもSONYや東芝に比べるとまだまだという感じ。実際には必要充分なんですけど、それを必要と思わせるうまさがない。スーパーのコージーコーナーか、銀座高野のショーケーキ。どちらもうまいけど値段が違うのはそれを容認できるだけの演出がケーキに存在しているから、という風に同じ画質改善機能でも東芝はレゾリューションなんとか、ソニーはDRC-MF V3なんていうかっこいい名前が付いています。
悩んだこと。
まず店頭での画質比較っていうのは悲しいほど役に立ちません。正確に言うとその店舗がどの程度の照明を使っているかによります。秋葉原ヨドバシでやっと薄暗いところでのZXシリーズの展示があって、それでやっとLEDエリア制御の有用性を見いだせたくらいですから、もし実際に近い環境でみたいと望むなら、それなりに店舗をはしごするしかないでしょうね。
ZX9000と比較した機種:SONY XR1 ZX8000 Z8000
XR1の46Vはもう製造中止になったようですが、もしZX9000の発売がなければおそらくこれにしていたと思います。ただ前のアクオスを買ったときに2003年発売のものを買っていたので2008年発表のXR1はやや買うにしては古すぎるというところが引っかかりました。何度も見て、かなり良かったと思いますXR1
継続機が出たらZX9000を売っぱらおうかなとさえ思わせるほどです。逆にZX8000は画質はまあまあにしてもXR1のライバルには全くふさわしくない。ディープラグーンが好きになれませんでした。他にもZX9000にもいえるんですが、電源コードが直付けであったりZシリーズとスタンドの違いくらいしかデザインに差異がなかったり(CELL REGZAが最高峰として存在するからなのかもしれませんけど)XR1のような明確なフラグシップらしさというものを感じないんですよね。ZX9000(Z9000)から、ディープラグーンの部分が落ち着いた感じに(ほとんどフレームは真っ黒に近い)なったのでまあまあ良くなったとは思いますけど。ディープラグーンはZX9000(Z9000)では有って無いような存在感にまでさせられちゃってます。むしろ真っ黒にしてもいいんじゃないのかと思うほど。
あと細川さんだったか、誰かもおっしゃってましたけど、スタンドの葉っぱみたいなデザインはちょっと・・・47Z9000のほうがかっこいいね。
デザインデザイン。ここまでそんな事ばかりですけども、正直昨今の液晶はどれを買ってもほどよく高画質です。少なくとも私の目には。
だからもうデザインとか操作性とか、そういうところで差をつけてくるフェーズに入っていると個人的には思うんですよね。数年前からの液晶からの買い換えでも幸せになれると無責任ながら保証できます。それくらい今のテレビはどれを買ってもだいたい同じ(笑
もちろんこだわったなりに差異はあるんですけどもね。
46ZX9000の詳細レビュー
画質についてはファーストインプレッション通りですが、ZX8000のレビューでLEDエリア制御が保守的な動作にとどまっていると指摘されていましたが、それはそうだと思います。具体的に言うと、たとえばライブ映像があって、真ん中に中島美嘉がいてスポットライトで照らされているような映像で、左半分と右半分のバックライトは消灯しても良さそうなものですが、実際には照度が極限まで絞られる程度です(CCFL機種あるいはエリア制御無しと比較すればやはり黒さは違うけど)なので暗室ではわずかな液晶からの光の漏れが見えます。もっともこれでもかなり高コントラストだと実感は出来ますが。
真っ暗になるときは入力切り替えをしたとき(笑
あるいは画面が暗くフェードアウトしたときですね。ある程度の黒が描写される場面でないとバックライトは消灯しないようです。古畑任三郎のOPではLEDがどんな制御をしているかをよく感じることが出来ます。買った人は見てみてね。
たとえば全体的に曇りのシーンでは意外とLEDが働きません。もちろん全く働かないわけではないんですが、感じにくいのです。明暗が離れていて、それぞれ(暗いところと明るいところ)が固まっている方が得意みたいです。
これ以降はZ,ZX共通ですが、レグザリモコン2は微妙!Z8000の時からもこの操作性に不満でしたが改善されてません!
具体的に言うと「録画リスト」とかいう聞き慣れないボタンを押したとき、内蔵HDD(ZシリーズはLANハードディスクやUSBハードディスク)に録画してあるものが出てくるのですが、レグザリンクで機材を選択しDLNAでX90の映像を再生しているときに押すと、X90の中身がリストされる。一見親切そうですが、再生を停止してから「録画リスト」を押すと内蔵HDDの方が出てくる。要するに再生を停止したらいちいちレグザリンクからDLNA機材を選択しないといけないというわけです。もっとスマートなやり方があるはず。
それとたとえば録画リストを眺めていて閉じたくなったとき、いちいち終了を押す。SONYではホーム内での操作はホームのボタンで抜けられるので操作が自然なんですね。さっとXMBに表示される録画してあるものを確認して抜けたいとき、ホームから指を動かす必要がないSONYに対してレグザは律儀に終了を押させる。とても面倒です。録画リストを再び押したら画面が閉じてほしい。
(ちなみに設定メニューは設定メニューボタンで閉じることが出来る。とても謎だ)
とにかく操作性は悪いですね。でも逆にそれが楽しいのも事実ですけど。細かいのが嫌いな人には、あるいは直感的に操作性を求める人にはレグザは向かないですね。
画質設定にしても幅が広すぎて、とにかく買ってから数時間はこの画質設定と戦うことになると思います。おまかせ設定でもまあまあいいんですけど、9000からその機能のボタンをリモコンから削除したとおり、やはり自分で調節してナンボのREGZAだと思うので是非いじってください。