20世紀の忘れ物 [2371号]
2008年11月3日 日常本日の日記
(徒然なる日記にアクセスが集中すると困るので固有名詞がイニシャルになってます)
著作権を知らなかったのか、あるいは著作権におぼれたのか。
ひとりの名プロデューサーの逮捕の報道は、人々を嘆かせそして古傷を触られたような、不思議な心地がしたのかも知れません。朝の報道は、憂鬱な曇り空とはそう反して充分な驚きを与えてくれました。芸能人の堕落は、それ自体がひとつの番組として成立してしまうほど数多くあり、人々はそのたびに批判したりファンは悲しんだりと、喜怒哀楽の操作をしてきましたが、既におきまりのフレーズかも知れないが、改めて『まさか、彼が捕まるとは』
Can you celebrate?をはじめさまざまな名曲を生み出した才能は、誰にも否定できないでしょう。90年代は彼の折り紙が付くと、どんな駄作でも誰もが飛びついて離さなかった、そんな時代でした。それはファンや大衆だけではなく、レコード会社も。
しかし流行とは流れ行くと書くようにいつかは消えて無くなるもの。ビッグビジネスを夢に見て広げた大風呂敷は、時代の流れと共に流され消えてしまった。
しかし現実には流行は消え去っても債務は流れることが無く、むしろ不渡りで、またプライベートで抱えていた女性問題によって、貴重な印税も上流でせき止められるなど、彼が詐欺に至るまでの外堀はどんどんと埋められていたのかも知れません。
もし手っ取り早く大金を手にするなら、著作権をうっぱらおう・・・。実にシンプルな考え方でK氏は出資を募ったのか、あるいはもっと恣意的に、著作権制度の複雑さ(例えば作詞・作曲・歌、全部作ってSONYからCDを出したとしても、その作った歌の著作権を人に10円で売り渡すことが出来ない───著作隣接権があって)を利用したのか、それは虚しい法廷で明かされることでしょう。当時の状況とか背景がそこで再生されるのです。
せっかく生み出された曲達はもはや再生されることはないのでしょうか?報道で歌が流されるたびに著作権使用料がK氏に支払われるのが皮肉なものです(*1)。
(*1:実際には放送局はJASRACと包括的な曲の利用を出来るように契約しており、個別のBGMにたいして使用料幾らという契約ではない)
90年代は80年代とも、この2000年代とも違う独特の雰囲気がありました。このころに作られた作品は今でも評価されるものもあれば、古くさいものもある。バブルが崩れて、人はみえない金融よりも実体のある自分とか個人を見つめ直すようになりました。織田裕二の「お金がない!」はそんな世相を反映したドラマでした。
90年代はCD業界にとっては最後のバブルだったのかも知れません。金融は90年の頭に崩れ去りましたが、それでも殆どの人々は堅実に生きていたので、バブル崩壊の蚊帳の外。でも日本を支配するぼんやりとした退廃的雰囲気が、どんなときも。や愛は勝つなどの典型的一発ソングを生み出し、人々はCDにお金を使うようになりました。
ちょうどこの前からバンドブームがあり(小話だけど槇原はこのバンドブームのあおりを受けてSONYをオーディションに落ちている)
人々がドラムスにいらだちを覚えたころにいわゆる小室ブームがやってくる。小室ブーム時代の曲は今でいえばどれに近いかな・・・。
ちょうどコンピュータ技術も進んで、個人でも高音質のDTM環境を作れるくらいだったから、オリコンの上位を独占できる楽曲を大量生産するのは、あとは才能さえあればとても簡単だったのでしょう。
「CD業界の最後のバブル」と書いたのは、携帯もパソコンもまだよちよち歩きの市場でしかなく、それらはもっぱらビジネスマンの仕事道具として、大衆の手軽な娯楽装置としてはまだまだ機能不足だったからです。
昨日見たテレビの話、というのはもう時代遅れかも知れない。高校生達に耳を傾けると昨日見たドラマよりも、昨日見たニコニコ動画の話をしているのかも知れない。それは例え少数でも、テレビから人を奪ったのは事実で、今の感覚でこの90年代を眺めると、くだらない曲が流行っていたんだな、という感想を持つ方は多そうだけど、それはそういう時代だったから・・・としか表現できませんね。
個人と個人のやりとりの距離が今ほど手軽に広げることはなかった時代でしたから、点と点でコアな音楽ファンがいたとしても、それをリンクさせるのは容易いことではなかった。しかし今はmixiで出来る。
今は適当に作られた曲は簡単に見破られてしまいますが、当時はまだインターネットがそんなにメジャーではなかったのでそういうことはあまりなかった。
2000年から急にCDが売れなくなったのはDSLの普及と関係があるのでしょうか。あるいは人々が小さなコンピュータをもち、あまねく情報を把握できるようになったからか。
点と点の本物志向の人たちはJ-POPの欺瞞さを吹聴していった。またエイベックスが不用意にネット文化に触れたことがさらにそれを加速させ、エイベックスは今や商業音楽会社の代名詞になってしまった。
K氏の逮捕は個人的な犯罪だが、要因を考えると20世紀の終演を今やっと見た気がしました。2000年が20世紀だとか2001年が21世紀だとか、そういう境界を確認しているうちに21世紀になり、そして気がついたら音楽シーンは簡単なサンプリングで作られたヒップホップみたいなよくわかんないものから、何を聴いても常に新曲な気がする古典アーティストや、時々電通が仕掛ける流行歌とか、マイナーアーティスト、そしてネットだけで活動するアーティストなど、音楽シーンは一面的なものから多面的なものへと進化していった。そんな中で小室ブームはもはや20世紀の忘れ物としての存在となり、かつてはトップにおかれていたCDも、部屋の何でも箱に投げ込まれ、日の目を見ることはもう無いのでしょう。
今日のマミ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
サビは最近押し入れの中がお気に入りのようで、ずーっとこもって寝ています。
でも夕食になるとひょっこり現れダイニングテーブルに前足を載せる。
でもマミはサビに怒ったままなので僕の部屋にいるとか、遠くから眺めているだけ。
マミが孤立しないように配慮しているけど、うーん、なかなか疲れるな。
もっともマミに仲良くなれというのもこちらのエゴですからねぇ。
(徒然なる日記にアクセスが集中すると困るので固有名詞がイニシャルになってます)
著作権を知らなかったのか、あるいは著作権におぼれたのか。
ひとりの名プロデューサーの逮捕の報道は、人々を嘆かせそして古傷を触られたような、不思議な心地がしたのかも知れません。朝の報道は、憂鬱な曇り空とはそう反して充分な驚きを与えてくれました。芸能人の堕落は、それ自体がひとつの番組として成立してしまうほど数多くあり、人々はそのたびに批判したりファンは悲しんだりと、喜怒哀楽の操作をしてきましたが、既におきまりのフレーズかも知れないが、改めて『まさか、彼が捕まるとは』
Can you celebrate?をはじめさまざまな名曲を生み出した才能は、誰にも否定できないでしょう。90年代は彼の折り紙が付くと、どんな駄作でも誰もが飛びついて離さなかった、そんな時代でした。それはファンや大衆だけではなく、レコード会社も。
しかし流行とは流れ行くと書くようにいつかは消えて無くなるもの。ビッグビジネスを夢に見て広げた大風呂敷は、時代の流れと共に流され消えてしまった。
しかし現実には流行は消え去っても債務は流れることが無く、むしろ不渡りで、またプライベートで抱えていた女性問題によって、貴重な印税も上流でせき止められるなど、彼が詐欺に至るまでの外堀はどんどんと埋められていたのかも知れません。
もし手っ取り早く大金を手にするなら、著作権をうっぱらおう・・・。実にシンプルな考え方でK氏は出資を募ったのか、あるいはもっと恣意的に、著作権制度の複雑さ(例えば作詞・作曲・歌、全部作ってSONYからCDを出したとしても、その作った歌の著作権を人に10円で売り渡すことが出来ない───著作隣接権があって)を利用したのか、それは虚しい法廷で明かされることでしょう。当時の状況とか背景がそこで再生されるのです。
せっかく生み出された曲達はもはや再生されることはないのでしょうか?報道で歌が流されるたびに著作権使用料がK氏に支払われるのが皮肉なものです(*1)。
(*1:実際には放送局はJASRACと包括的な曲の利用を出来るように契約しており、個別のBGMにたいして使用料幾らという契約ではない)
90年代は80年代とも、この2000年代とも違う独特の雰囲気がありました。このころに作られた作品は今でも評価されるものもあれば、古くさいものもある。バブルが崩れて、人はみえない金融よりも実体のある自分とか個人を見つめ直すようになりました。織田裕二の「お金がない!」はそんな世相を反映したドラマでした。
90年代はCD業界にとっては最後のバブルだったのかも知れません。金融は90年の頭に崩れ去りましたが、それでも殆どの人々は堅実に生きていたので、バブル崩壊の蚊帳の外。でも日本を支配するぼんやりとした退廃的雰囲気が、どんなときも。や愛は勝つなどの典型的一発ソングを生み出し、人々はCDにお金を使うようになりました。
ちょうどこの前からバンドブームがあり(小話だけど槇原はこのバンドブームのあおりを受けてSONYをオーディションに落ちている)
人々がドラムスにいらだちを覚えたころにいわゆる小室ブームがやってくる。小室ブーム時代の曲は今でいえばどれに近いかな・・・。
ちょうどコンピュータ技術も進んで、個人でも高音質のDTM環境を作れるくらいだったから、オリコンの上位を独占できる楽曲を大量生産するのは、あとは才能さえあればとても簡単だったのでしょう。
「CD業界の最後のバブル」と書いたのは、携帯もパソコンもまだよちよち歩きの市場でしかなく、それらはもっぱらビジネスマンの仕事道具として、大衆の手軽な娯楽装置としてはまだまだ機能不足だったからです。
昨日見たテレビの話、というのはもう時代遅れかも知れない。高校生達に耳を傾けると昨日見たドラマよりも、昨日見たニコニコ動画の話をしているのかも知れない。それは例え少数でも、テレビから人を奪ったのは事実で、今の感覚でこの90年代を眺めると、くだらない曲が流行っていたんだな、という感想を持つ方は多そうだけど、それはそういう時代だったから・・・としか表現できませんね。
個人と個人のやりとりの距離が今ほど手軽に広げることはなかった時代でしたから、点と点でコアな音楽ファンがいたとしても、それをリンクさせるのは容易いことではなかった。しかし今はmixiで出来る。
今は適当に作られた曲は簡単に見破られてしまいますが、当時はまだインターネットがそんなにメジャーではなかったのでそういうことはあまりなかった。
2000年から急にCDが売れなくなったのはDSLの普及と関係があるのでしょうか。あるいは人々が小さなコンピュータをもち、あまねく情報を把握できるようになったからか。
点と点の本物志向の人たちはJ-POPの欺瞞さを吹聴していった。またエイベックスが不用意にネット文化に触れたことがさらにそれを加速させ、エイベックスは今や商業音楽会社の代名詞になってしまった。
K氏の逮捕は個人的な犯罪だが、要因を考えると20世紀の終演を今やっと見た気がしました。2000年が20世紀だとか2001年が21世紀だとか、そういう境界を確認しているうちに21世紀になり、そして気がついたら音楽シーンは簡単なサンプリングで作られたヒップホップみたいなよくわかんないものから、何を聴いても常に新曲な気がする古典アーティストや、時々電通が仕掛ける流行歌とか、マイナーアーティスト、そしてネットだけで活動するアーティストなど、音楽シーンは一面的なものから多面的なものへと進化していった。そんな中で小室ブームはもはや20世紀の忘れ物としての存在となり、かつてはトップにおかれていたCDも、部屋の何でも箱に投げ込まれ、日の目を見ることはもう無いのでしょう。
今日のマミ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
サビは最近押し入れの中がお気に入りのようで、ずーっとこもって寝ています。
でも夕食になるとひょっこり現れダイニングテーブルに前足を載せる。
でもマミはサビに怒ったままなので僕の部屋にいるとか、遠くから眺めているだけ。
マミが孤立しないように配慮しているけど、うーん、なかなか疲れるな。
もっともマミに仲良くなれというのもこちらのエゴですからねぇ。
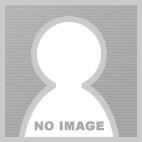
コメント